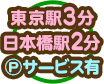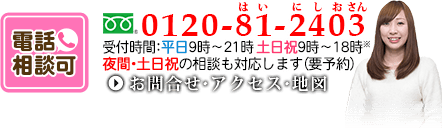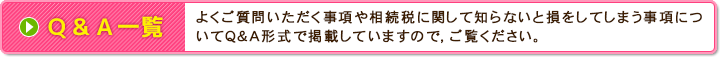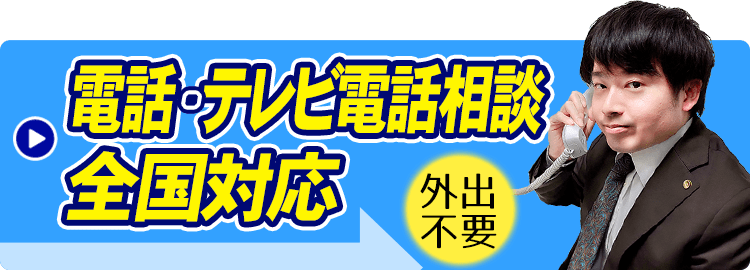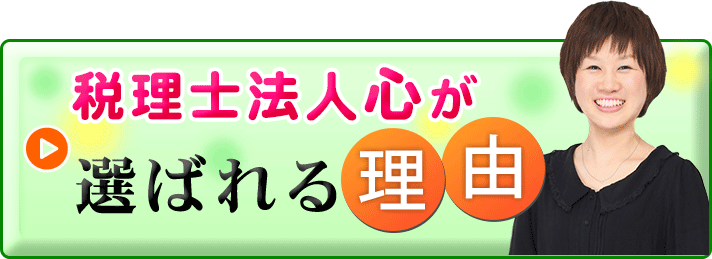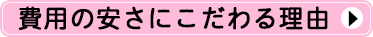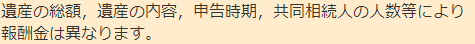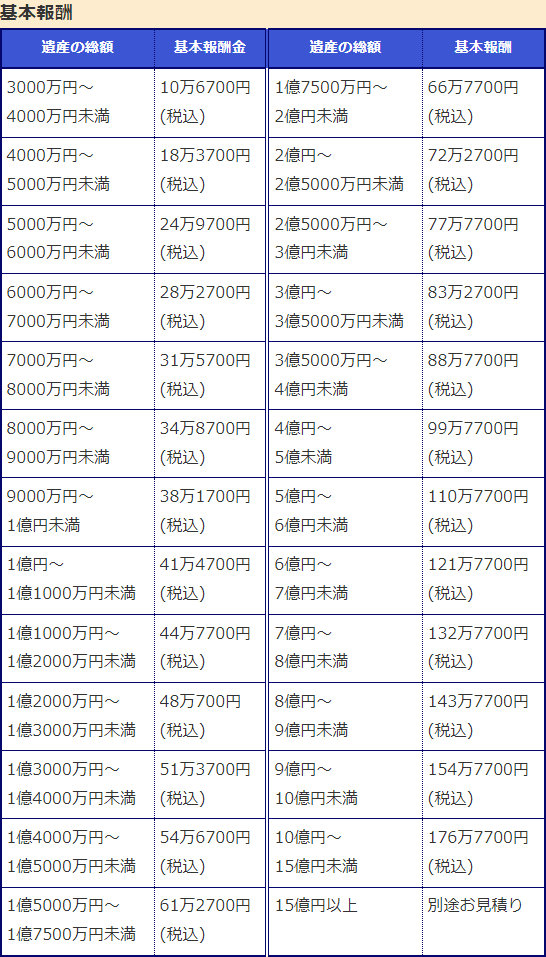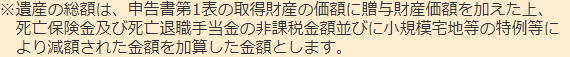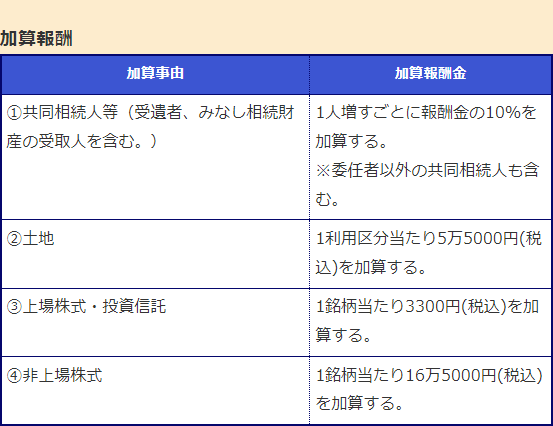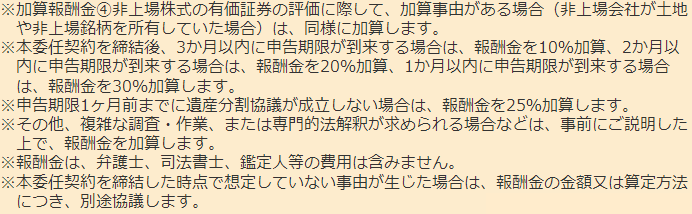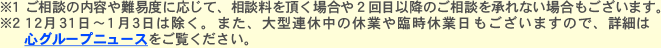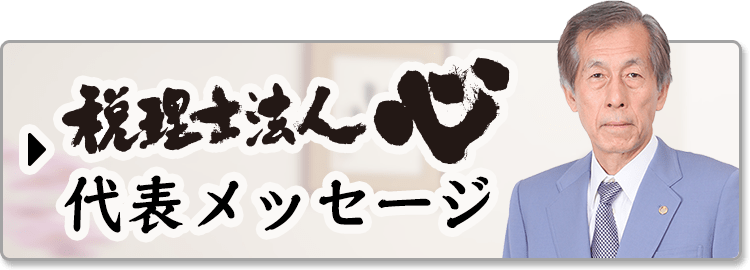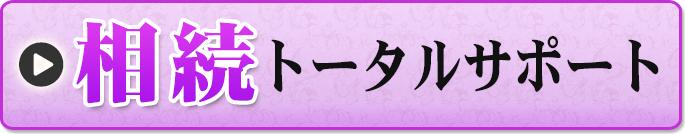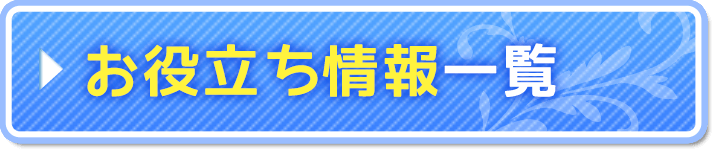「相続税申告」に関するお役立ち情報
相続税のみなし相続財産について
1 相続税の課税対象となる財産にはどのようなものがあるか
相続税がかかる財産にはどのようなものがあるでしょうか。
金銭的価値があるものはすべて相続財産ですので、相続税の課税対象となります。
反対に、借金などのマイナス財産は、相続税の計算の際に差し引くことができます。
相続税の課税対象となる相続財産の種類としては、まず、土地や建物などの不動産があります。
この不動産には、自宅土地建物だけでなく、貸家、貸宅地、店舗、田畑、山林などがあります。
次に、現金、預金があります。
株式や、投資信託、公社債などの有価証券、貸付金、売掛金などの債権、被相続人が個人事業主の場合は、棚卸資産や一般動産等の事業用財産も相続財産に当たります。
その他、自動車、家具、貴金属・宝石等の家庭用動産や、ゴルフ会員権、電話加入権、特許権や著作権などの知的財産権も相続税の課税対象になる場合もあります。
また、相続税の課税対象として、みなし相続財産もあります。
2 相続税のみなし相続財産とはどのような財産をいうのか
みなし相続財産とは、被相続人が直接遺した財産ではないのですが、実質的には相続や遺贈によって取得したことと同様な経済的効果があると認められる財産として、相続財産とみなされるものです。
みなし相続財産は、相続税の課税対象となります。
みなし相続財産に当たるものとして、生命保険金、死亡退職金、個人年金など定期金に関する権利などがあります。
3 生命保険金と死亡退職金には非課税枠があります
みなし相続財産である死亡保険金と死亡退職金には、非課税枠が適用される場合があります。
非課税額は「500万円×法定相続人の数」で計算します。
この計算式は、死亡保険金も死亡退職金も同じですし、非課税枠の金額までは相続税の課税対象とはなりません。
4 生命保険金の注意点
生命保険金がみなし相続財産として相続税が課税されるためには、被相続人が保険料を負担している必要があります。
生命保険の契約の内容によって課税される税金が変わってきますので注意が必要です。
5 死亡退職金の注意点
死亡退職金は、受け取るタイミングによって、課税される税金が変わります。
具体的には、①死亡後3年以内に遺族が受け取った場合は、相続税が課税されます。
他方で、②死亡後3年経過後に遺族が受け取った場合は、受取人の一時所得として所得税が課せられるので注意が必要です。
相続税の申告期限はいつか 相続税の申告後に新たな財産が見つかった場合