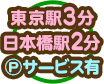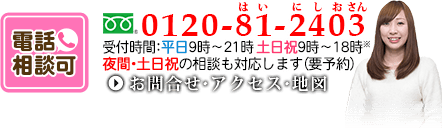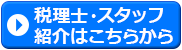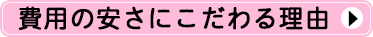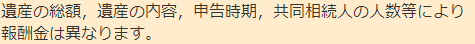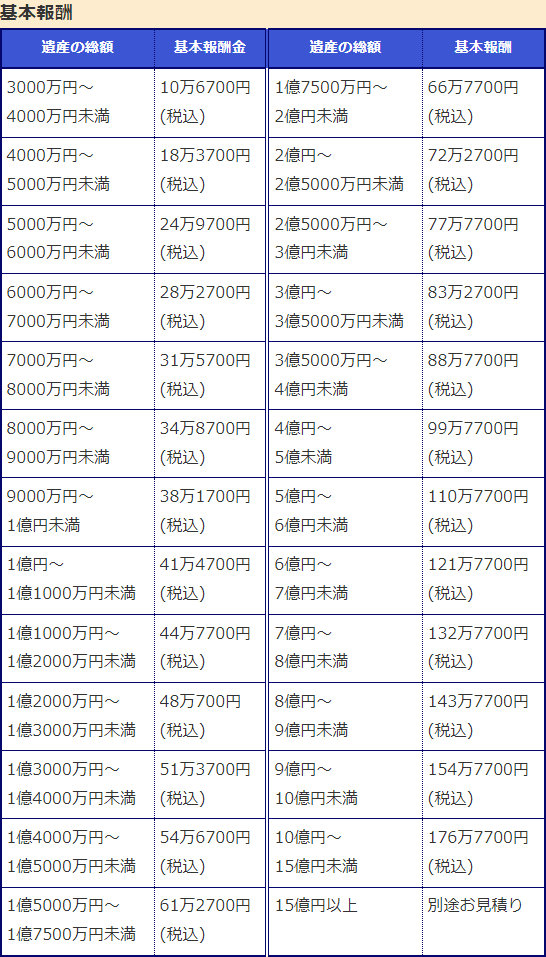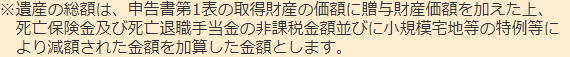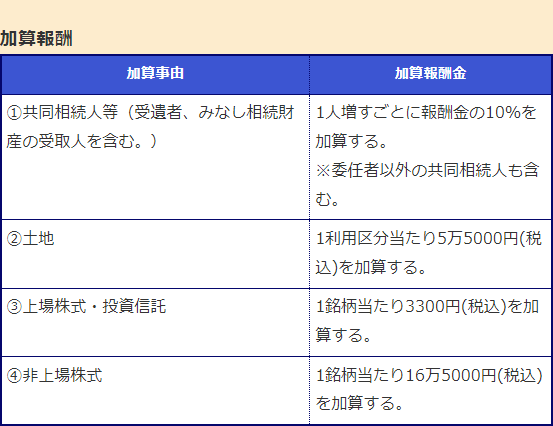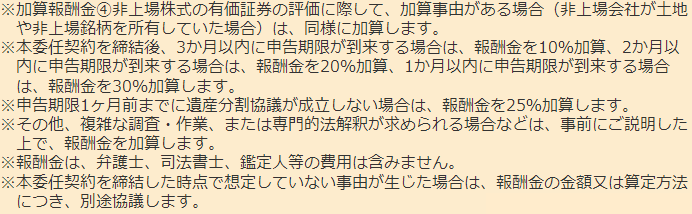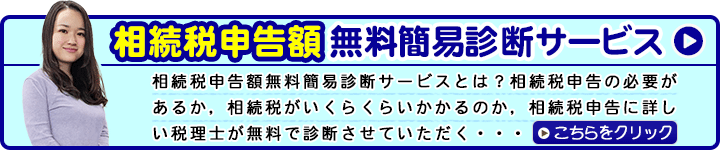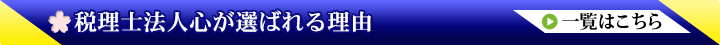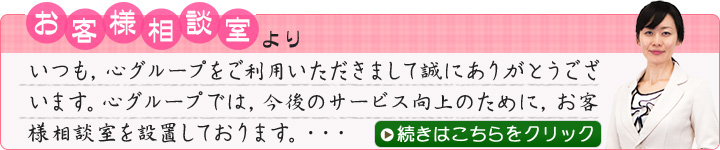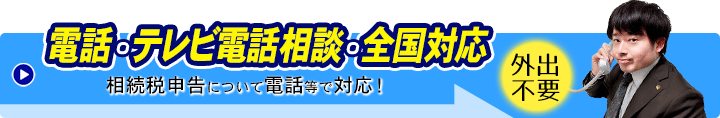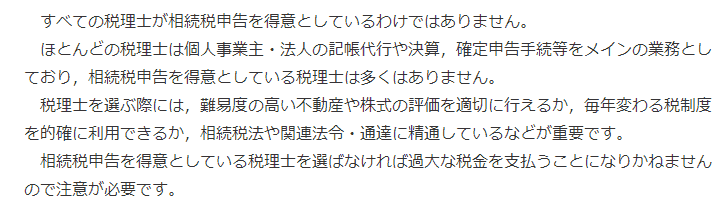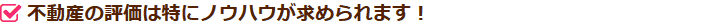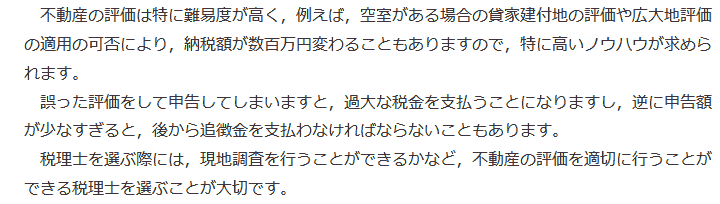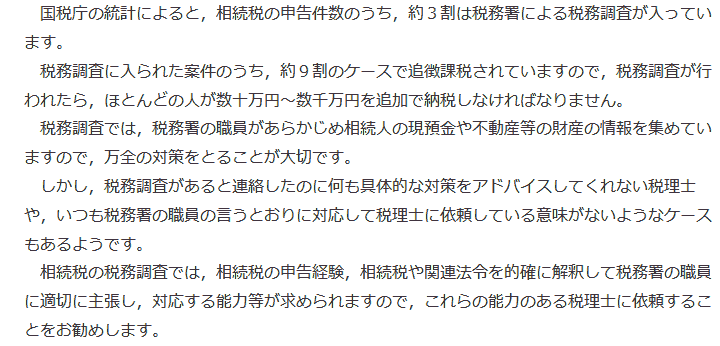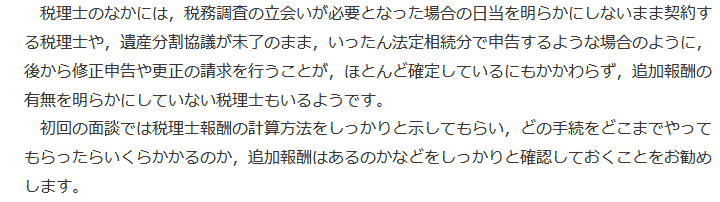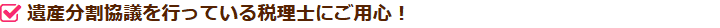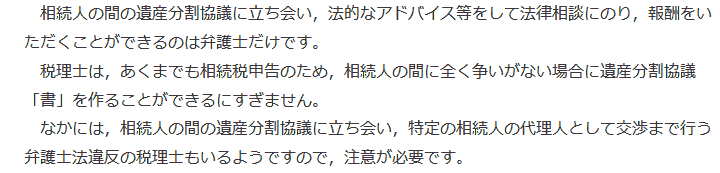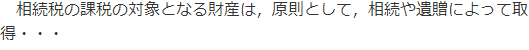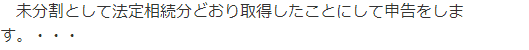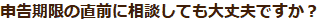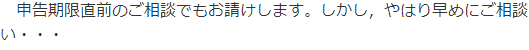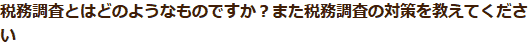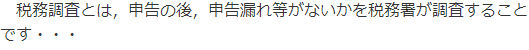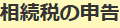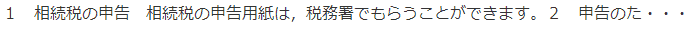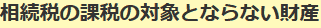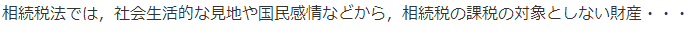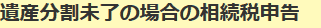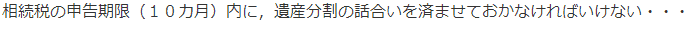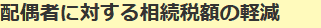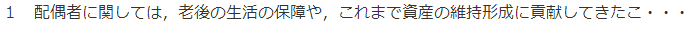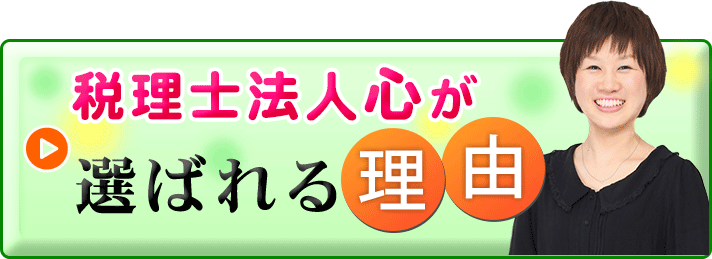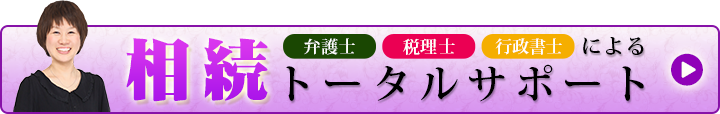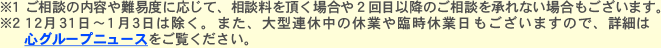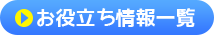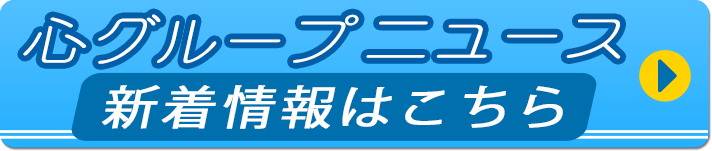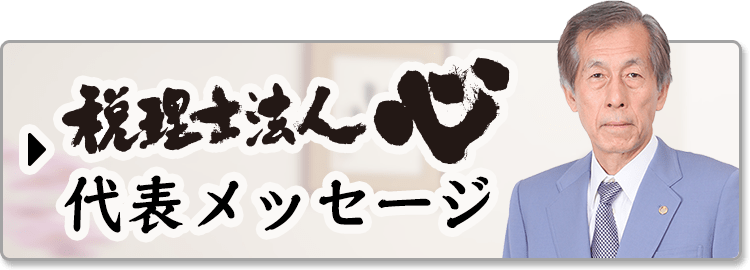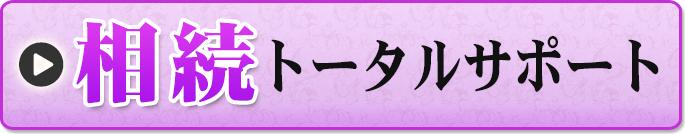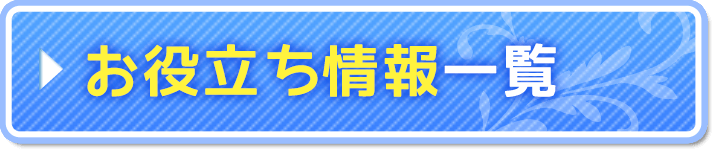-
1
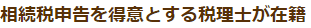
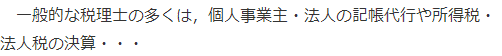 続きはこちら
続きはこちら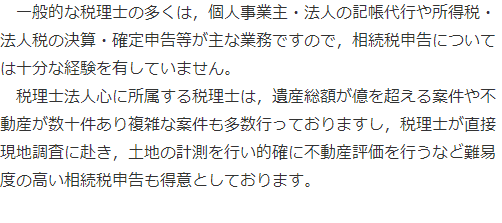
-
2
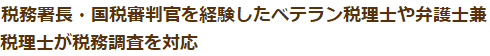
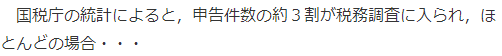 続きはこちら
続きはこちら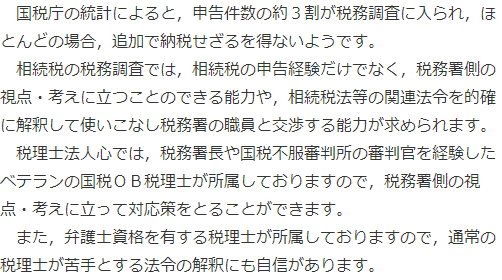
-
3
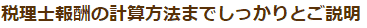
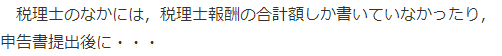 続きはこちら
続きはこちら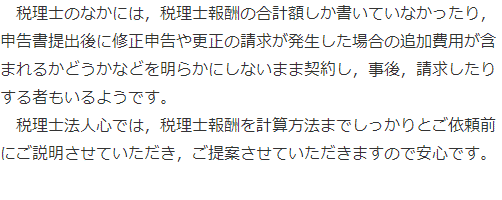
-
4
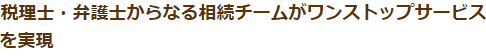
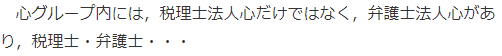 続きはこちら
続きはこちら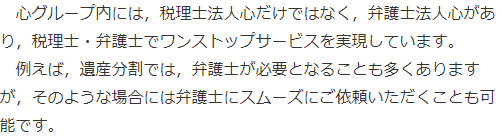
-
5
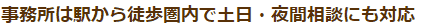
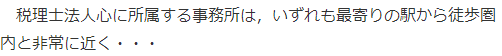 続きはこちら
続きはこちら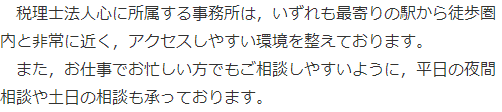
東京で相続税の相談を検討中の方へ
相続税の申告を日頃から取り扱っており、得意とする税理士が対応いたします。相談にあたってその他にもいくつか当法人の強みがありますのでこちらもご覧ください。
サイト内更新情報(Pick up)
2026年2月17日
相続税対策
タワーマンションが相続税対策になるのですか?
不動産を購入することで、相続税を減らすことができると聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。なぜ不動産を購入することが相続税対策になるのか、疑問に思われる方・・・
続きはこちら
2026年1月23日
相続税対策
生前贈与を活用した相続税対策
相続税は、被相続人が所有していた土地・建物、預貯金等の財産から、借入金、未払金等の債務を引いた後の金額に課税されます。このため、被相続人が所有していた財産を減らすこと・・・
続きはこちら
2025年12月24日
相続税対策
生前贈与による相続税対策を行う場合に利用できる制度
生前贈与によって相続税対策をしようと考えたとき、利用できる制度はいくつかあります。そもそも相続税は、相続開始時における相続財産について課されるものです。ということは、生前・・・
続きはこちら
2025年11月12日
相続税申告
相続税を期限内に納付できない場合
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に行います。たとえば、1月15日に死亡した場合には、その年の11月15日・・・
続きはこちら
2025年10月14日
相続税計算
相続税の路線価に関するQ&A
一般的には、①実勢価格、②公示地価・基準地価、③固定資産税評価額、④相続税評価額があります。不動産の相続税評価額を算定する際、土地の評価において路線価を用いることがあり・・・
続きはこちら
2025年9月3日
相続税計算
自分で相続税を計算する場合の注意点
相続財産を取得した方は、その取得した財産の価額に応じた相続税を支払うことになります。例えば、みなし相続財産を含む相続財産の評価額が相続税の基礎控除の範囲を超えた場合・・・
続きはこちら
2025年8月1日
相続税制度
相続税の物納制度を利用するための条件
相続税は、申告期限までに申告と納付をすることになります。相続税は、原則として現金で一括して納付しなければなりません。しかし、相続したのが不動産ばかりなど、相続財産の構成に・・・
続きはこちら
最新の情報はこちらから
当サイトでは相続税に関するお役立ち情報を掲載し、定期的に内容の更新も行っています。
駅近くにある事務所です
当法人の事務所はどこも駅から近い場所にあります。関東には、東京駅の近くにも事務所がありますので、相続税申告でお悩みの方もお気軽にご相談ください。
税理士に相続税申告について相談する際の流れ
1 早めに相続税申告の準備に着手することが重要です

相続税の申告は、相続が発生し、そのことを知った時から10か月以内に行う必要があります。
遺言があるかどうかや、遺産分割協議が成立するなど遺産の分け方が決まっているかどうかに関係なく、10か月以内の申告と納付が義務付けられています。
相続後は、相続財産を詳細に調査してその内容を把握し、自分が相続税を支払う必要があるかどうか確認することから始まり、戸籍謄本や財産に関する資料等、申告に必要な書類を集めたりするなど様々なことを期限内にしなければなりません。
相続税の申告期限と必要書類については、こちらをご参照ください。
そのため、10か月の申告期限直前になってから税理士に相談しても、その期限までに間に合わない可能性があります。
期限が近づいてから慌てて確認すると、誤った対応をしてしまう危険性がありますので、なるべく早く税理士に相談しておくことをおすすめいたします。
2 相続税の相談をする税理士を選ぶ
相続税について相談するにあたっては、相続税申告を得意とする税理士をお選びください。
税金といっても、相続税の他にも様々な種類があり、これら税金の種類に応じて、税理士にもそれぞれ専門分野があるためです。
特に相続税申告で一番難しいポイントは、土地など相続財産をどのように評価するかという点であり、相続税額に反映されるため非常に重要です。
相続税に詳しくない税理士に依頼をしてしまうと、適切に申告できないおそれがあります。
そのため、相続税を日頃から扱っており、得意としている税理士に依頼されることをおすすめします。
3 初回相談の流れ
⑴ すべての相続で相続税申告が必要となるわけではない
相続税には基礎控除が定められているので、相続財産が基礎控除額の範囲内であれば相続税申告は不要であり、相続税を支払う必要はありません。
このように、相続税は、一定額以上の遺産がある場合に発生する税金であるため、家族構成や相続財産の内容や評価額によっては、相続税の申告が不要な場合があります。
他方、基礎控除額を超える遺産がある場合は、原則として相続税の申告と納税が必要になります。
⑵ 最初に相続税申告が必要かどうかを確認します
相続税申告について、税理士に初めて相談する際は、被相続人や自分の家族構成と遺産の内容について詳細をお伺いし、相続税の申告が必要かどうかをまず確認します。
税理士が基本的な情報を確認した後、相続財産が基礎控除の額を上回るため相続税の申告が必要な場合、相続税がどれくらいの額になるのかを大まかに試算します。
併せて、申告のためのスケジュールについて確認し、特に相続税の申告の期限に注意をしながら、今後の流れを説明します。
4 初回相談後の流れ
一般的に、相続財産の概要や評価額が不明な場合など、初回相談だけでは、相続税の申告が本当に必要かどうか分からない場合があります。
そのような場合は、相続税の申告が必要かどうかを判断するために、戸籍謄本や除籍謄本等の相続関係が分かる書類、相続財産が分かる書類、例えば、不動産の名寄帳、登記情報、銀行の残高証明書や通帳など、より詳細な相続財産に関する資料が必要になります。
税理士によっては、ご相談の前や初回の相談の際に、相続税申告のために必要な資料の一覧表を渡して、その資料が集まり次第、2回目の相談を行い、より詳しいご説明をすることもあります。
相続税の対象となる財産
1 被相続人が亡くなった時点において所有していた財産

相続税の申告をするにあたって、どのような財産が課税の対象となるのでしょうか。
万が一申告が漏れてしまった財産があると、税務調査の対象となったり、加算税などのペナルティを受けたりするおそれがあります。
そのため、どのような財産が相続税の対象となるのかをしっかりと把握しておく必要があります。
基本的には、被相続人が亡くなった時点において所有していた財産が相続税の課税対象となります。
具体的には、土地や建物などの不動産、株式や公社債などの有価証券、預貯金や現金などのほか、金銭に見積もることができる全ての財産です。
2 みなし相続財産
被相続人の死亡に伴い支払われる「死亡保険金」や「退職金」などは、相続によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、「死亡保険金」や「退職金」のうち、「500万円×法定相続人数」までは非課税となります。
3 被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
被相続人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合、その財産は相続税の課税対象となります。
この場合、贈与の時の価額を相続価格に加算します。
4 被相続人から相続開始前の一定期間内に取得した暦年課税適用財産
被相続人から相続などによって財産を取得した人が、被相続人が亡くなる前3年以内(令和6年1月1日以降の贈与から、3年の期間が段階的に7年に延長されています)に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。
その場合、加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。
この期間内であれば、贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算されることになり、贈与税の基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算されることになるため、注意が必要です。
参考リンク:国税庁・贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
5 相続税の対象とならない財産
反対に、相続税の対象とはならない財産もあります。
例えば、墓地や墓石、仏壇、仏具等礼拝に使用する物は、相続税の対象とはなりません。
ただし、仏具等でも高価であり投資的価値の高いものは課税の対象となることがありますので注意が必要です。
また、相続や遺贈によって取得した財産を相続税の申告期限までに地方公共団体に寄附したものについても、相続税はかかりません。
その他に、心身障害者共済制度の給付金を受ける権利や、公益事業のために使用される財産等についても、相続税は非課税となります。
6 相続税の申告については税理士へご相談ください
どのような財産が相続税の対象になるのか知りたい、財産の評価の仕方で困っている等の場合には、税理士へご相談ください。
税理士は相続税を申告するために必要な相続財産の調査にも対応できます。
当法人には相続税を得意とする税理士がおり、ご相談については原則無料で承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
相続税申告が必要な場合
1 基礎控除額を超える場合

相続財産の総額が基礎控除額を上回る場合には、相続税の申告が必要になります。
相続税の基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)で算出されます。
遺産の総額が上記算定式によって算出された基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要となります。
2 特例を使う場合
小規模宅地の特例や配偶者控除の適用を受ける場合には、申告をすることが要件のひとつとなっています。
特例を適用した結果、納税額がゼロとなる場合でも、相続税の申告が必要となりますのでご注意ください。
⑴ 配偶者控除の場合
配偶者控除とは、配偶者が相続によって取得した財産のうち、1億6000万円までは相続税が課税されないという制度です。
また、1億6000万円を超える場合でも、配偶者の法定相続分までは相続税は課されません。
この配偶者控除の適用を受ける場合には、相続税の申告書又は更正の請求書にその適用を受ける旨とその計算に関する明細を記載し、必要な書類を添付して期限内に税務署に提出しなければなりません。
⑵ 小規模宅地の特例の場合
小規模宅地の特例とは、一定の要件に当てはまる土地を相続した場合に、その一定面積まで、相続税の計算をする際の評価額を50%または80%減額できるという制度です。
例えば、被相続人が住んでいた土地を配偶者が相続する場合には、特定居住用宅地として、330㎡までは土地の評価を80%減額することができます。
この小規模宅地の特例を適用する場合にも、相続税の申告書又は更正の請求書にその適用を受ける旨とその計算に関する明細を記載し遺産分割協議書等の必要書類を添付して、期限内に税務署に提出しなければなりません。
3 相続税申告をしないとどうなるか
相続税は、相続発生後10か月以内に申告・納税しなければなりませんが、その期限に間に合わないと、様々な不利益を負うことになります。
例えば、上記特例は基本的に申告することにより受けることができるため、申告しなければ適用されません。
そのため、特例を利用すれば基礎控除額を下回り、相続税が0円だからといって申告をしないでいると、特例を利用しないケースとみなされます。
さらにその状態で相続税の申告期限を過ぎてしまうと、特例も利用できず、無申告加算税や延滞税などのペナルティも課税されることになります。
相続税の申告が遅れた場合のペナルティについては、こちらをご覧ください。
期限内に相続税の申告と納付をするため、できるだけ早いうちから準備を進めておくことが大切です。
4 相続税申告が必要か分からない方
自分が相続税の申告をする必要があるのか、どのくらい相続税を納めなければならないのか、特例を利用することができるのか等について、よく分からないという方もいらっしゃるかと思います。
その場合、まずは一度税理士にご相談いただくことをおすすめします。
相続税申告が必要となった場合には、期限に間に合うよう計画的に準備を進める必要があります。
そのため、税理士へのご相談は、相続後できるだけ早めがよいです。
当法人には相続税申告を得意とする税理士がおりますので、お気軽にご相談ください。
相続税を申告・納付する義務者について
1 相続税の納税義務者とは

相続税の納税義務者は、相続、遺贈、死因贈与によって財産を取得した人が対象となっています。
参考リンク:国税庁・相続税がかかる場合
また、上記に該当する場合のうち、住所や国籍要件等によって、さらに「無制限納税義務者」と「制限納税義務者」の2種類に分かれます。
参考リンク:国税庁・相続人が外国に居住しているとき
⑴ 無制限納税義務者
無制限納税義務者は、日本国内と海外の財産のどちらにも相続税の納付義務がある人を指します。
無制限納税義務者には細かい要件があります。
例えば要件のひとつに、被相続人又は相続人が相続時に日本国内に住所を有している場合というものがあります。
無制限納税義務者に該当すると、海外に所在する被相続人の財産についても日本の相続税が課税されることになります。
⑵ 制限納税義務者
一方、制限納税義務者は、被相続人が日本国内に保有する財産に対してのみ相続税の納付義務がある人を指します。
例えば、相続発生時に被相続人および相続人が、ともに過去10年間に日本国内に住所を有していないような場合に該当します。
制限納税義務者の場合には、被相続人が有していた財産のうち、日本国内にあるものについてのみ課税がされます。
2 納税義務者に当たる場合でも相続税の納税が不要な場合
相続税の納税義務者であっても、一定の場合には相続税の申告・納税が不要となることがあります。
まずは、相続人が相続した財産が基礎控除額を下回る場合です。
相続税の基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で算出され、遺産の総額がこの基礎控除額以下である場合には、相続税の申告・納税は不要となります。
また、基礎控除以外にも未成年者控除や障害者控除等の各控除制度があります。
参考リンク:国税庁・未成年者の税額控除
参考リンク:国税庁・障害者の税額控除
これらの控除制度を利用して相続税がゼロになる場合には、申告・納税は不要となります。
その他に、配偶者控除や小規模宅地の特例によって相続税がゼロになる場合については、相続税の申告は必要ですが、納税は不要となります。
3 相続税の申告・納付が必要かを知りたい方へ
相続によって財産を取得したので、相続税を払う必要があるのか知りたい方や、特例や各種控除を使うことができるのかよく分からないという方は、お気軽にご相談ください。
相続税に関して、当法人では原則無料でご相談を承っています。
また、無料で相続税額を簡易診断するサービスも行っており、そちらもご利用いただけますので、まずはお問い合わせください。
税理士に相続税の相談をする際に大切なこと
1 相続税に強い税理士に相談する

税理士に相続税の相談をする際にはまず、相続税に強い税理士をお選びください。
相続税の申告は、税理士ごとに違った計算結果になるといわれるほど、税理士の力量が求められます。
事案によっては、数千万円単位で納税額が変わってしまうこともあります。
加えて、相続税は、実際に起きた相続に関する税金の計算だけでなく、その後の相続、いわゆる二次相続についても考慮して申告を行うことが必要となってきます。
そのため、たまにしか相続税申告を扱わないという税理士ではなく、相続税申告の実績と知識が豊富な税理士に相談することが大切です。
当法人には、相続税に注力し、得意とする税理士が在籍しています。
これまでに多くの相続税申告に対応していますので、まずはご相談ください。
2 幅広く対応してくれるところがおすすめ
また、相続税の申告は、税法だけでなく、民法、不動産、金融、様々な分野の知識が求められます。
例えば、土地の評価の場合、単純に全面路線価に土地の面積を乗じれば評価額が出せるわけではありません。
土地の間口はどこになるのか、奥行きは何メートルになるのか、道路にはいくつ接しているのか等の個別的な評価をする必要があります。
このように不動産一つとっても、考慮すべき事項が多岐にわたり、かつ、それぞれの事項に応じた資料の読み込みが必要となりますので、不動産に関する知識が必須となります。
税以外の分野についても精通している税理士や、他の分野の専門家と連携が取れる税理士に相談することも大きなポイントとなります。
3 相談時には相続に関する情報をまとめておく
税理士に相続税について相談をする際には、①被相続人及び相続人の情報、②相続財産の情報、③相続債務の情報、④相続財産の分け方についての情報をまとめておくと、スムーズに相談が進むかと思います。
これらの情報は、相続税の金額を算出する際や、特例や控除の利用可否を検討する上で必要となってきます。
もちろん、最初のご相談からこれらの資料をしっかりと揃えておく必要はありませんので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
① 被相続人及び相続人の情報
被相続人の出生から死亡までの戸籍があるとよいですが、最初の相談であれば、手書きの家系図があれば十分です。
相続税の申告において、相続人が何人いらっしゃるのかというのは、納税義務の有無や相続税額の概算をする際に重要となります。
② 相続財産の情報
大きく分けて、不動産、預貯金、有価証券、保険金に関する情報をまとめておくのが良いです。
不動産は固定資産税および都市計画税の課税明細書、預貯金は通帳や残高証明書、有価証券は証券会社の報告書、保険金は保険証書又は支払い明細があると、財産の把握がスムーズになります。
③ 相続債務の情報
住宅ローンといった被相続人の借入金のほか、亡くなられる前後の病院代や薬代、葬式費用の領収書をまとめておく必要があります。
これらは、相続税の計算をする際に、遺産総額から控除できるためです。
参考リンク:国税庁・相続財産から控除できる債務
葬儀費用については、火葬費用、遺体の運搬費用、葬式費用、お布施代は控除することができます。
一方で、香典返しの費用や墓地の借り入れ費用、初七日や法事にかかった費用については控除することはできません。
④ 相続財産の分け方について
小規模宅地の特例等の特例の適用ができるかどうか、また、申告期限までに分割が間に合うかどうかを判断するために必要な情報となってきますので、大まかにでも遺産の分け方のご意向を固めてから相談にお越し頂けますとスムーズに相続税についてご説明できます。
相続税申告が適切にできないとどうなるか
1 相続税の申告を適切に行わなかった場合に起こること

相続税の申告を適切に行わないと、追加で税金を払わなければならない等のペナルティが課されることがあります。
相続税の申告を適切に行わなかった場合というのは、大きく2つのパターンに分けることができます。
ひとつは、相続税の申告期限までに申告を行わなかった場合です。
もうひとつは、本来申告しなければならない金額よりも少ない金額で相続税の申告を行ってしまった場合です。
このいずれか、または両方に該当する場合、その内容によって延滞税、無申告加算税、過少申告加算税、重加算税というペナルティが課されることがあります。
2 延滞税
相続税の申告期限よりも後に申告を行った場合や、申告期限までに申告をしたものの後から修正申告書を提出した場合には、申告期限から相続税の納付を行った日までの期間に応じて、延滞税を支払わなければなりません。
延滞税は、早く納付するほど金額は小さくなりますので、相続税の申告が遅れてしまったとしても、できるだけ早く納付するようにしましょう。
延滞税の金額の計算は複雑ですが、国税庁のホームページで詳しく説明がなされています。
参考リンク:国税庁・延滞税の計算方法
3 無申告加算税
特段の事情がないにもかかわらず、期限までに相続税申告をしなかった場合には、無申告加算税が課されます。
ただし、相続税の申告期限から2週間以内に申告をした場合、無申告加算税はかかりません。
申告期限から2週間以上経過してから、税務署の調査が入る前に相続税の申告、納付をした場合には、無申告加算税は5%となります。
申告期限までに申告をしないまま税務署の調査が入り、その後で相続税申告をした場合には15%、税額が50万円超~300万円以下については20%、300万円を超える部分については30%の無申告加算税がかかります。
4 過少申告加算税
相続税申告期限までに申告し、申告書に記載されたとおりの相続税を納付しても、その相続税の申告書に記載された税額が、本来納めるべき税額よりも少なかった場合には過少申告加算税が課されます。
自主的に修正申告をし、正しい税額を納付した場合には、過少申告加算税は課せられません。
申告した税額が少ないことを税務署から指摘されたあとで修正申告をした場合には、納税額に対して10%の加算税がかかります。
さらに申告したときの税額と50万円とくらべて大きい金額を超える部分については、15%の加算税がかかります。
5 重加算税
相続税の支払いを免れるために意図的に少ない金額で申告したり、申告自体をしなかった場合には、悪質性が高いとされるため、重加算税が課せられます。
相続財産の隠匿(いわゆる財産隠し)や、相続財産の存在を裏付ける書類の偽装した場合には、追加で支払う相続税の35%が重加算税として課されます。
相続税申告をせず、相続税が課せられないように相続財産を隠匿したり、相続財産を裏付ける書類を偽装した場合には、相続税総額の40%もの重加算税が課されます。
6 適切な相続税申告を行うために
以上のようなペナルティを課されることがないよう、相続税を期限内に適切に申告することは重要です。
適切な申告を行うためには、相続税を得意とする税理士に、できるだけ早い段階で一度ご相談ください。
当法人には、相続税申告を集中して取り扱い、得意とする税理士がいますので、東京の方もまずはご相談ください。
遺産分割と相続税の関係
1 遺産分割が成立しない場合の相続税への影響

相続では、相続人同士で強い意見対立が生じることがあり、一向に遺産分割が成立に至らないといったことも起こり得ます。
遺産分割が成立しないと、各相続人が取得する財産の額が決まらず、相続税のす計算ができません。
さらには、遺産分割が成立するかどうかによって特例等の利用可否が変わるため、相続税の総額が大きく異なってくるケースもあります。
2 小規模宅地等の特例を利用する場合
被相続人が居住したり、事業に用いたりしていた宅地については、評価額が大きく減額されることがあります。
具体的には、被相続人が居住していた宅地については、これを配偶者や同居親族等が取得した場合に、330㎡を限度面積として、土地の評価額を8割も減額することができます。
他にも、被相続人が事業に用いていた宅地については、事業を引き継いだ親族が取得した場合に、400㎡を限度面積として、土地の評価額を8割も減額することができます。
さらに、被相続人が貸付をしていた土地についても、貸付事業を引き継いだ親族が継続して貸付事業を行う場合には、200㎡を限度面積として、土地の評価額を5割も減額することができます。
ただし、この貸付事業用宅地の小規模宅地の特例の場合には、過度な租税回避行為を防止するために、平成30(2018)年4月1日以後の相続から相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された土地は原則として適用の対象外となっていますので、この点は注意が必要となります。
土地の単価が大きいと、小規模宅地等の特例を用いることにより、土地の評価額を大きく減額でき、相続税の額を大きく軽減できる可能性があります。
相続税を軽減できる小規模宅地等の特例について詳しくは、こちらもご覧ください。
もっとも、小規模宅地等の特例を用いる場合には、前提として、その土地について遺産分割が成立している必要があります。
成立していなければ、小規模宅地等の特例を用いることができず、申告期限の段階では、本来の相続税を納付しなければならなくなってしまいます。
このように、遺産分割が成立するかどうかによって特例を利用できるかどうかが変わり、納付すべき相続税の額に大きな違いが出てくることがあります。
3 配偶者の税額軽減を利用する場合
他にも、配偶者の税額軽減を用いることができれば相続税額の負担を大きく減らすことができますが、これを適用するには遺産分割が成立していることが前提条件になってきます。
参考リンク:国税庁・配偶者の税額の軽減
4 遺産分割がまとまらない場合の相続税申告
以上のとおり、遺産分割が成立しているかどうかによって、特例等の利用可否が変わり、申告期限の段階で納付すべき相続税の額が大きく異なってくる可能性があります。
なお、協議が成立していないものの、上記の小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減を利用したい場合、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する方法があります。
しかし、その場合でもいったんは特例等の適用前の金額で相続税を納める必要があります。
そうすることで、申告期限後3年内に「遺産分割が確定」した場合は、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用した金額を計算し、納め過ぎた税金について「更正の請求」をすることができます。
ただし、更正の請求にも期限があり、「分割確定」から4か月以内となりますので、十分ご注意ください。
5 お悩みの場合はお早めにご相談ください
相続税の負担を軽減できる特例や控除を利用するには、遺産分割が完了していなければなりません。
相続税の申告や納付に大きな影響を及ぼしますので、このことを相続人間で共有した上で、遺産分割の早期成立を目指した方が良い場合があります。
早期に認識を共有するためにも、お悩みの場合は、早めに専門家に相談されることをおすすめします。
当法人の場合、連携する弁護士法人心にて遺産分割に関するお悩みをご相談・ご依頼いただくことができますので、相続税申告が必要なのに遺産分割がまとまらずお困りの場合にもご連絡ください。
税理士の選び方
1 相談したい内容に詳しい税理士を選ぶ

一言に税理士といっても、様々な業務を扱っています。
税金には、相続税をはじめ、所得税、法人税など多くの種類があり、それぞれ必要な知識やノウハウが違います。
それゆえ、税理士であれば誰に相談してもよいという訳にはいきません。
相続税の申告が必要な場合に、相続税に詳しくない、あるいは普段は扱っていないという税理士に相談をしてしまうと、対応に時間がかかってしまい期限に間に合わなかったり、適切な申告ができなくなってしまったりすることも考えられます。
そこで、相続税について相談したいのであれば、相続税に詳しい税理士というように、ご自分の相談したい内容に詳しい税理士を選ぶ必要があります。
特に相続税に関しては専門性が高く、土地などの財産評価が問題となったり、特例や控除の適用によって税額に大きな影響が出るなどしますので、相続税に詳しい税理士をお選びいただくことが重要なポイントとなります。
2 人柄も大事
専門家としての能力も大事ですが、質問がしづらいような雰囲気ですと、大切なことを聞き逃したり、必要なコミュニケーションが取れずに情報不足となり、適切な申告ができなくなってしまうかもしれません。
税理士を選ぶ上では、その人柄も重要になるかと思います。
特に、税理士には普通は他人に話さないような資産のことを相談するため、やはり信頼できる人柄であるほうが安心です。
また、何度も連絡を取る必要がある場合には、気難しい人だと話すたびに気疲れしてしまうかもしれません。
話しづらいからと相談を先延ばしにしていたら期限に間に合わなくなった、税金の申告不備につながってしまったというようなことになれば、税理士に依頼した意味がなくなってしまいます。
気になったときに気軽に相談できる関係が築けるという点で、税理士の人柄も大切となってきます。
3 他の専門家と連携が取れる税理士の強み
相続税について相談をする際、実際の悩み事というのは、税金の問題だけにとどまらないこともあります。
例えば、相続税は相続の揉め事とセットになることが多いですが、税理士は揉め事に介入できないため、普通は、相続税に関することは税理士に、相続の揉め事に関することは弁護士にというように、それぞれに相談をしなければなりません。
しかし、弁護士と連携が取れる税理士であれば、異なる事務所に足を運び、それぞれ個別に相談をすることなく、相続の問題に対応することが可能となります。
このように連携できる事務所であれば、色々なところに相談する手間がかからないですし、相続の問題について税金以外の多方面からのアドバイスを受けられることが期待できます。
4 まずは会ってみる
税理士を探す際、税理士事務所のホームページに書いてあることは、どれも同じに見えてしまい、どこに頼んでいいか分からないかもしれません。
しかし、実際に会って話してみることにより、その分野への詳しさ、説明の分かりやすさ、人柄など気づくことは多いと思います。
無料相談を実施している事務所もありますので、それらを利用して、まずは税理士に会い、実際に話をしてみることをおすすめします。
5 相続税について税理士をお探しの方へ
当法人では、原則として、相談料無料で相続税のご相談を承っておりますので、まずは気軽に相談をしていただけるのではないかと思います。
相続税の案件を集中して扱い、得意とする税理士がご相談に対応いたします。
できるだけ丁寧に分かりやすくご説明することを心掛けておりますので、費用のことや手続きで気になる点があれば遠慮なくお尋ねください。
東京駅近くに事務所を構えていますので、相続税について税理士をお探しの方はまずご連絡ください。
相続税に詳しい税理士に依頼するメリット
1 必要な情報を的確に集め、適切に申告を行ってくれる

相続税申告を依頼する場合には、相続税を得意とする税理士に依頼することをおすすめします。
相続税を得意とする税理士なら、申告に必要な情報を的確に集めた上で財産評価や税額の計算を行い、適切に申告を行ってくれることが期待できるからです。
というのも、相続税の申告においては、実際に複数の税理士が申告を行うと、それぞれ違った金額になることがあるためです。
事案によっては、納付すべき税額が何千万円単位で異なることもあります。
このようなことが起きる原因は、必要となる情報が多種多様であり、税理士によってどこまでの情報を集めることができるかについて差が出ることにあります。
ですから、相続税申告の実績と経験が豊富な税理士に依頼することが大切になります。
また、相続税の申告は、税の知識だけではなく法律や不動産、金融等の様々な知識が必要となります。
税以外の知識についても豊富な税理士に依頼することもポイントになります。
2 必要となる資料のアドバイスが受けられる
相続税の申告をするためには、沢山の資料が必要となります。
相続税の申告には期限が定められていますので、期限内に必要な資料を漏れなく集めなければなりません。
税理士に必要となる資料を確認した上で、必要な資料を早く集めることがスムーズな相続税申告のポイントになります。
例えば、戸籍謄本、預金残高証明書、預貯金の通帳、遺言書、保険金支払通知書、固定資産課税台帳(名寄帳)、固定資産税評価証明書、固定資産税・都市計画税の納税通知書、葬式費用の領収書といった資料が必要となります。
相続税申告の際の必要書類と集め方についてはこちらで説明をしていますので、ご参照ください。
相続税を得意とする税理士は、どのような資料が必要であるかも熟知していますので、このような資料の収集もスムーズに進められるかと思います。
3 二次相続についても相談できる
例えば、父または母のいずれかが先に亡くなった場合、先に亡くなった方の相続を一次相続といいます。
その後、遺された父または母が亡くなった場合の相続を二次相続といいます。
相続税の相談をする際には、一次だけでなく、二次相続も見据えて相談することをおすすめします。
なぜなら、一次相続では相続税を安くすることができても、二次相続の際に税額が高額となってしまうというケースがあるためです。
二次相続で相続税額を抑えるためには、一次相続の段階でどのような対策をするべきか検討することが必要となります。
相続税に詳しい税理士であれば、一次相続だけではなく、二次相続まで見据えた提案をしてくれることが期待できます。
そのため、相続税に精通した税理士に依頼することをおすすめします。
4 相続税申告は当法人にお任せください
当法人には、相続税を集中的に扱い、得意とする税理士がいます。
相続税申告に注力している分、知識や経験を習得していますので、適切な申告ができるよう努めてまいります。
東京で相続税申告について税理士に依頼したいという方は、まず一度ご相談ください。
相続税の相談をするタイミング
1 相続税の申告には期限がある

相続税の申告は、被相続人が亡くなってから10か月以内に行わなければいけません。
さらに注意をしなければいけないのは、この10か月以内に「資料収集や土地評価などの複雑な計算を終えて」「納税までをしなければいけない」という点です。
申告をするだけではなく、納税まで済ませなければならないため、納税資金の準備まで念頭に入れておく必要があります。
期限が1~2か月後に迫ってから準備を始めたところ、資料集めや納税資金の準備が間に合わないケースも見受けられます。
相続税の申告期限はいつか、期限までに申告や納税をすることができない場合についてはこちらでも説明をしていますので、参考にしてください。
期限に間に合わせるため、相続税について税理士に相談する際は、相続後のできるだけ早い段階で、余裕を持ってご相談された方がよいかと思います。
2 相続税申告の準備には時間がかかる
相続が発生してすぐは、葬儀や市区町村役場での手続きなどで忙しかったり、気持ちの整理がつかなかったりと、なかなか相続税のことまで考える余裕がないかもしれません。
しかし、相続税の申告期限は決まっており、申告のための資料集めに時間がかかることも多いです。
どのような財産があるか、誰から誰への相続か等によって、集める資料が変わるため、その収集にかかる時間も様々ですが、例えば亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍を集めるだけで2~3か月かかってしまうことも珍しくありません。
集めた戸籍を使って銀行や市役所から証明書を取り寄せるとなれば、さらに時間がかかります。
相続税申告の際の必要書類と集め方については、こちらをご覧ください。
実際にいつから取り掛かるかは別にしても、早めに税理士に相談して、申告の準備にかかる時間の目安を把握しておき、直前で慌てないことが重要です。
四十九日法要が終わったら相談に行くくらいの心持ちでも良いかもしれません。
3 納税資金の準備も検討しておく必要がある
納付にあたり、遺産を使わずに納められる場合は問題ないのですが、遺産の中から相続税を支払う予定のときは注意が必要です。
銀行預金の解約など、相続手続きを行う際は、手続きに1~2か月の時間がかかります。
遺産分割が必要な場合は、話し合いがまとまるまでは預金の払戻しができないため、早期に話し合いをまとめるか、遺産とは別で納税資金を用意するかを検討しなければなりません。
そのため、早めに税理士に相談をして、納税資金の準備までを含めた申告手続きのプランを立てておくことをおすすめします。
4 遺産分割が終わらない場合も早めに相談して対応を検討する
相続税の税負担を軽減するため、配偶者控除や小規模宅地等の特例を利用したい場合、遺産分割が終わっていないとそれらの特例を利用することができません。
遺産分割が終わらない場合でも、一旦は10か月の時点で未分割申告を行い、相続税を納めなければなりません。
遺産分割が10か月以内にまとまらない場合の相続税対策については、こちらを参考にしてください。
遺産分割が終わっていないからといって相談を後回しにせず、終わらない場合にどのような対応をとるべきか、早めに税理士に相談しておくことをおすすめします。
当法人には、相続税を得意とする税理士が在籍していますので、申告が必要な方はお気軽にご相談ください。
遺産分割がまとまらない場合には、連携している弁護士が対応することも可能ですので、ご安心ください。
相続税のご相談から解決までにかかる時間
1 相続税申告はやるべきことが多い

相続税の申告のためには、戸籍収集、財産調査、財産評価、特例適用の検討、申告書作成などやるべき作業が多くあります。
それぞれにどれくらいの時間がかかるかは、相続人の人数や財産の種類・量によって大きく変わりますが、少なくとも数か月はかかるケースが多いでしょう。
相続税申告には期限がありますので、これらの調査や評価、書類収集・作成等は、期限内に終わらせなければなりません。
相続税の申告期限と必要書類について、こちらの記事も参考にしてください。
それぞれの作業について、どのようなことを行うのか、かかる期間の目安等についてご説明いたしますので、それを踏まえた上で早めに準備を始めることが重要です。
2 申告にあたって行うこととかかる時間の目安
⑴ 戸籍収集
相続人の人数が間違いないかを確認するため、相続税申告書には戸籍を添付する必要があります。
この戸籍は、被相続人が生まれてから亡くなるまでに作成された全ての戸籍が必要になります。
本籍地を頻繁に移動されている方など、必要となる戸籍の数が10通〜20通になることも珍しくありません。
戸籍は市役所等の市区町村の窓口で取得することができますが、取得する戸籍の数が多いと、戸籍を集めるだけでも1〜2か月かかる場合もあります。
⑵ 財産調査
申告漏れとならないために、相続税の申告書には財産を漏れなく記載しなければなりません。
そのためには、網羅的な財産調査が必要となるので、金融機関への照会や不動産の調査を行います。
また、株式などの有価証券や保険金も申告の対象となるため、こちらも調査します。
財産調査を始めたところ、相続人が知らなかった預貯金口座や、過去に投資のために購入して被相続人本人も忘れていた不動産が見つかるケースもあります。
調査の対象となる財産が多ければ多いほど、時間がかかってしまうことも多いです。
⑶ 財産評価
現金・預貯金と異なり、不動産や上場されていない株式は、その価値がどれくらいになるのか、評価を行う必要があります。
不動産、特に土地については、面積と路線価(1平方メートルあたりの値段)を計算した後、土地の形・奥行、道路の幅、法律上の利用制限などにより増減されるため、評価には時間がかかります。
不動産の相続税評価額の計算方法について詳しくは、こちらをご覧ください。
また、非上場の株式も会社の保有財産や決算書等を踏まえて正確に行う必要があり、時間がかかってしまうこともあります。
⑷ 特例適用の検討
相続税には、相続税が減額される特例が多数あります。
特例の中には、併用できるもの・できないものがあるため、どの特例を組み合わせたら最も相続税が安くなるかは、財産状況等により人それぞれです。
そのため、どの特例を利用するかについて網羅的に検討する必要があります。
3 相続税申告の準備は余裕をもって行うことが大切
以上のように、集めなければならない戸籍の数、調査や評価が必要な財産の種類等によっては時間がかかることもあるため、余裕を持って準備を行うことが大事です。
相続税申告の期限である10か月という期間は長いように感じますが、申告の準備の他にもご葬儀・法要、相続手続き、遺産分割の話し合いなどを行っていると、あっという間に時間が無くなってしまうことも多いです。
万が一期限に間に合いそうになかったり、十分な調査ができないまま期限がきてしまったという場合には、期限を延期する手続きをしたり、いったん仮で申告するといった対応が考えられます。
しかし、延期する場合でも、10か月以内に税務署に対して延長の手続き自体は行わなければなりませんし、一度申告したものを修正・更正する場合にも期限があります。
また、後から修正等をする場合でも、ひとまずは仮で相続税を納めなければなりません。
例えば、遺産分割が終わっていないと特例の適用ができないため、後で払いすぎた分は返ってくるとしても、いったんは高額な税金を支払うためにお金を用意しなければならなくなってしまいます。
4 早めに相談をして相続税申告の見通しを立てる
相続税申告について余裕を持って行うためには、相続後のなるべく早い時期に一度税理士に相談して、今後のスケジュールや最初にやるべきことについて確認されることをおすすめします。
まずは相続税の申告が必要かどうかを判断し、申告が必要な場合には申告や納付に向けて今後のスケジュールを立てていく必要がありますので、お早めにご相談ください。
当法人では、原則相談料無料で相続税についてご相談いただけるほか、相続税額がいくらくらいになるのか無料で診断するサービスも実施しております。
相続税の申告でお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
相続税申告の特徴と当法人でのご相談について
1 相続税申告の特徴
⑴ 税理士によって納付すべき税額も変わることが多い
税金の申告は、必要となる情報を集め、決まった計算式等のルールを当てはめれば、いつも同じ申告額になるのではないかというイメージを持たれている方が多いかもしれません。
ところが、相続税の申告については、複数の税理士が申告を行うと、それぞれ違った計算結果になることがほとんどであり、事案によっては、何千万円単位で納付すべき税額が異なることもあります。
このようなことが起きる原因は、必要となる情報が多種多様であり、税理士がどこまでの情報を集めることができるかによって税額に差が出ることにあります。
このことは、土地の評価において特に顕著です。
ある税理士は、路線価図と登記簿だけを取得し、路線価と土地の面積だけを参照して、土地の評価額を算定するかもしれません。
別の税理士は、土地の図面を取得または作成し、土地の形状や公道への接し方を考慮して、土地の評価額を一定程度減額するかもしれません。
さらに別の税理士は、都市計画図を取得し、複数の容積率が適用されること、都市計画道路予定地であること等を考慮し、土地の評価額をさらに減額するかもしれません。
さらに別の税理士は、現地を訪れ、土地と公道との間に高低差があること、土地の上方に高圧線が存在すること等を考慮し、土地の評価額をいっそう減額するかもしれません。
特に東京の市街地では、土地の評価額が高額になることも多く、土地の評価の重要性が特に大きいといえます。
土地など、不動産の相続税評価額の計算方法については、こちらでも説明していますので参考にしてください。
このように、税理士がどこまでの情報を集めることができるかによって、申告書の内容が変わり、納付すべき税額も変わってくることになります。
このため、相続税の申告に際しては、どのようなポイントに着目し、どのような情報を集められるかが重要になります。
⑵ 遺産の分け方が決まらないと相続税の申告にも影響がある
遺産分割協議の内容は、相続税の申告にも、大きな影響を及ぼすこととなります。
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減については、申告期限までに遺産分割協議等によって財産の分け方が確定していなければ、当初申告の段階から特例を適用することができません。
当初申告の段階でこれらの特例が適用できなければ、一旦は多額の相続税を納付することになります。
事案によっては、特例を適用することができないために、納付資金の調達に苦慮する事態に陥ることもあります。
申告期限までに遺産分割が終わらない場合の相続税対策の注意点については、こちらもご覧ください。
このように、相続税の発生が予想される場合には、相続税申告の期限を見据えつつ、遺産分割協議を行う必要があります。
2 当法人での相続税申告のご相談
これらの相続税申告の特徴を踏まえ、当法人は、以下のような体制を整えています。
⑴ 相続税の申告を得意とする税理士
当法人には、相続税の申告を得意とし、集中的に取り扱っている税理士が在籍しています。
相続税申告を集中的に取り扱うことにより、例えば土地の評価についての経験が蓄積され、重要なポイントを把握する能力を高め、必要な情報を集める能力が養われると考えています。
相続税の申告を得意とする税理士が、適切な内容で申告できるよう尽力しています。
⑵ 弁護士との連携
当法人では、必要に応じて弁護士と連携することが可能です。
遺産分割協議が難航する事案では、連携している弁護士が、遺産分割協議の成立に向けた交渉も行っています。
3 東京駅近くで相談できます
税理士法人心 東京税理士事務所は、東京駅八重洲北口から徒歩3分の場所にありますので、相談にお越しいただきやすい立地です。
交通アクセスが良いという利点がありますので、東京やそのお近くにお住まいの方は、お気軽にご連絡ください。
事務所までお越しいただくことが難しい場合でも、お電話やテレビ電話で相続税について相談することができますので、まずはお問い合わせください。
相続税の計算の仕方
1 相続税の計算は税理士にお任せください

相続税の計算の仕方は複雑となります。
課税対象となる財産、控除の対象となるものを整理し、それぞれ評価を行った上で、相続税の税率を計算していきます。
計算の仕方について以下でご説明いたしますが、相続税がいくらかかるかよく分からないという方はお気軽に税理士にご相談ください。
当法人には相続税を得意とする税理士がいますので、お気軽に相談をしていただければと思います。
2 各人の課税価格の計算
次の⑴~⑶の相続税の課税財産の価額から、後記⑷~⑹の非課税財産の価額を差し引くと、各人の課税価格の計算ができます。
⑴ 相続または遺贈により取得した財産
本来の相続財産で、お金で見積もることができる財産をいいます。
⑵ みなし相続財産
本来は相続財産ではないが、相続や遺贈により取得した財産と同じとみなされ、相続税が課される財産をいいます。
例えば、死亡保険金や死亡退職金などがあります。
⑶ 相続開始前の一定期間内に被相続人から贈与を受けた財産
相続・遺贈によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年贈与された財産は、贈与により取得した時の価額で相続税が課税されます。
その贈与の際に、贈与を納めている場合は、二重に課税されないように、その贈与税額が相続税より控除されます。
なお、令和5年度税制改正により、令和6年1月以降の贈与については、原則として、相続開始前7年以内の贈与が相続税の課税財産となります。
⑷ 死亡保険金・死亡退職金
相続人が死亡保険金(被相続人が保険料を支払っていたもの)や死亡退職金(被相続人の死後3年以内に支給が確定したもの)を受け取った場合、それぞれについて、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。
ここでいう「法定相続人の数」とは、相続を放棄した相続人がいた場合には、放棄はなかったものとした場合の法定相続人の数となります。
また、被相続人に養子がいた場合、法定相続人に含められる普通養子の数は、実子がいる場合、養子は1人まで、実子がいない場合、養子は2人までとされています。
なお、相続人以外の人や相続放棄をした人が死亡保険金を受けることも可能で、その場合も相続税の課税対象となりますが、非課税枠はありません。
⑸ 相続税が非課税となる財産
墓所、仏壇、仏具、香典は、国民感情を考慮して相続税の非課税財産とされています。
⑹ 債務控除および葬式費用
借入金、未払医療費、未払所得税、未払住民税、未払固定資産税、通夜費用などは、債務控除および葬式費用として、財産価額から控除することができます。
これに対し、初七日・四十九日費用、香典返礼費用、墓地買入の未払金、税理士費用、遺言執行費用などは、債務控除および葬式費用の対象外とされています。
3 相続税の総額の計算
各人の課税価格の合計額から基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引き、課税遺産総額を算出します。
相続税の総額を計算するにあたっては、各相続人の実際の相続分にかかわらず、各人が法定相続分を取得したと仮定して計算し、その金額を合算します。
4 各人の相続税額の計算
前記3の相続税の総額を、各相続人の実際の遺産の取得割合に応じて按分し、各人の算出税額を算出します。
5 各人の納付税額の計算
前記4で計算した各相続人等の税額から、各個別事情に応じて加算・減算し、各人の納付税額を算出します。
相続税に関するお役立ち情報
当サイトでは様々な情報を掲載していますので、相続税についてお悩みをお持ちの方はどうぞ参考にしてください。