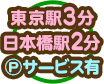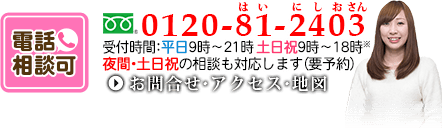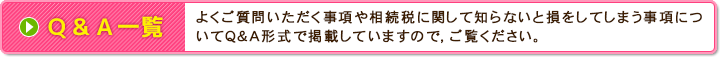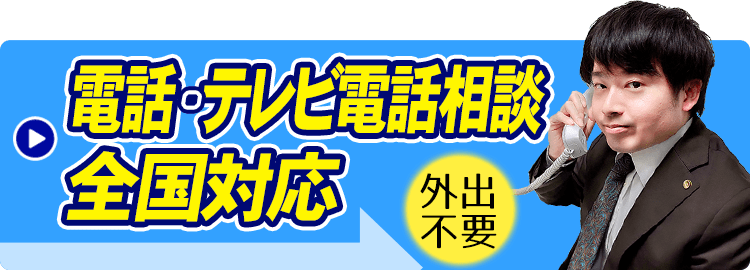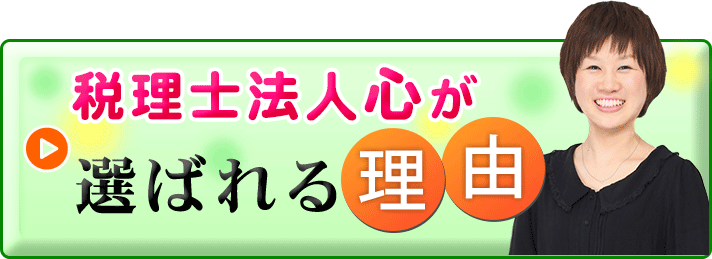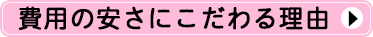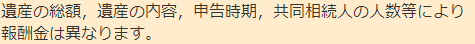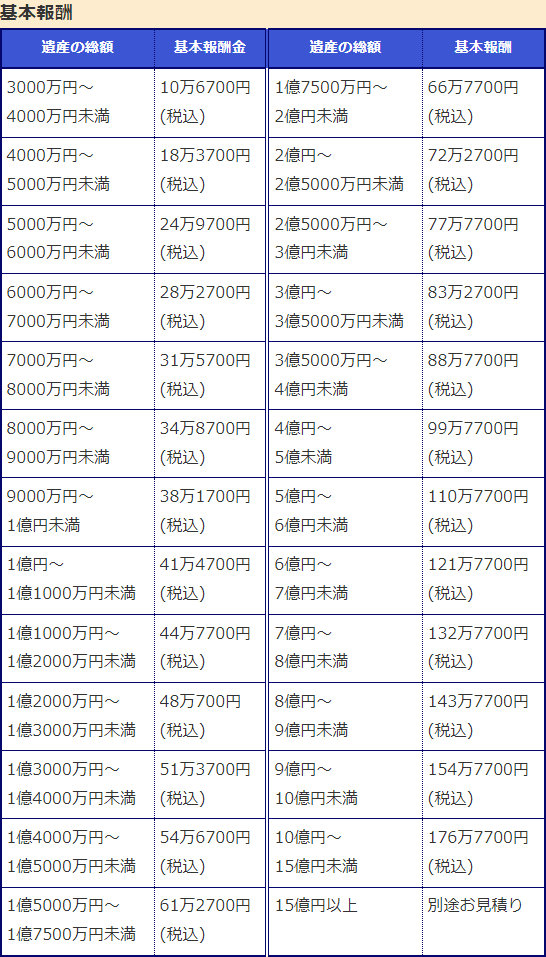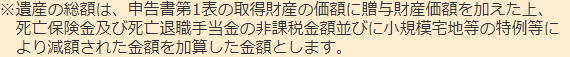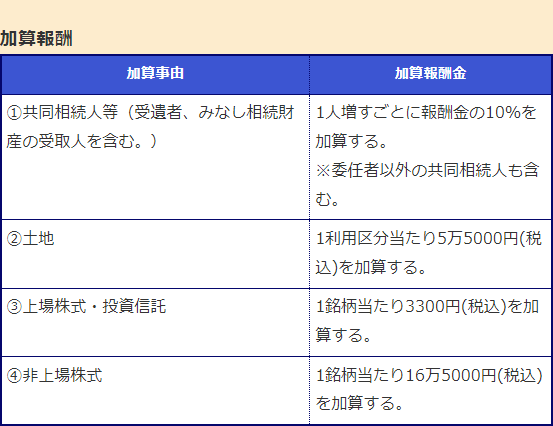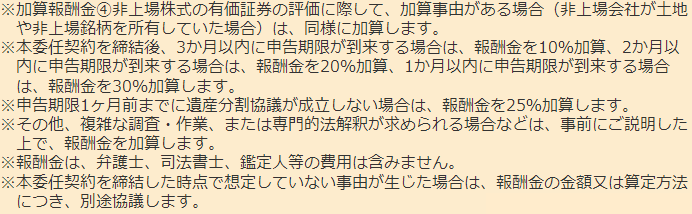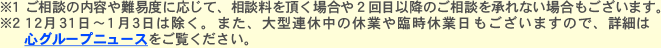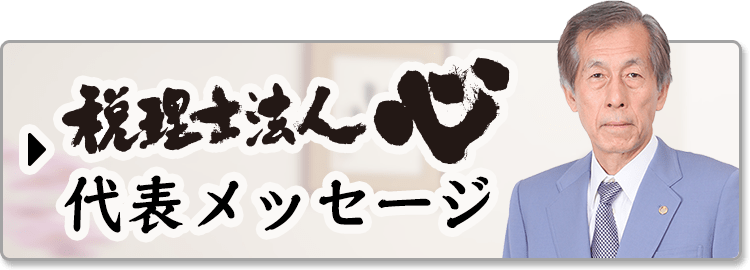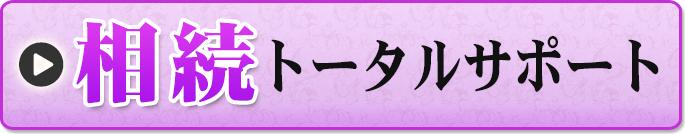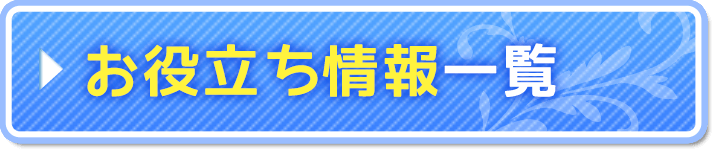「相続税対策」に関するお役立ち情報
生前贈与による相続税対策を行う場合に利用できる制度
1 生前贈与による相続税対策をお考えの方へ
生前贈与によって相続税対策をしようと考えたとき、利用できる制度はいくつかあります。
そもそも相続税は、相続開始時における相続財産について課されるものです。
ということは、あらかじめ相続人に財産を贈与しておけば、相続開始時の財産が減ることになり、相続税が少なくなります。
ただし、この生前贈与の額によっては贈与税が課されます。
贈与税の税率は相続税よりも高いため、贈与税が課されてしまうとより高い税率で税金を支払わなければならなくなります。
参考リンク:国税庁・贈与税の計算と税率(暦年課税)
たとえ相続税が少なくなったとしても、贈与税が多くなってしまえば意味がありません。
そのため、生前贈与をする場合には、いつ・誰に・いくら贈与するか、特例等の利用できる制度があるかについての検討が必要となってきます。
以降で、生前贈与による相続税対策として利用できる制度についてご紹介していきます。
2 暦年贈与
贈与税には、毎年(暦年)110万円の基礎控除があります。
110万円以下の贈与であれば、贈与税はかかりませんし、申告も不要です。
ただし、相続が開始した場合には、相続開始日から3年以内(令和6年1月1日以降から、3年の期間は段階的に7年に延長されます)の相続人に対する贈与は、基礎控除額以内であっても相続税の計算の基礎となる財産として加算されますので、注意が必要です。
参考リンク:国税庁・贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
このような加算を避けるためには、法定相続人ではない方、例えば法定相続人の子供(被相続人からすれば孫)、法定相続人の配偶者(婿養子等養子となっている場合は除く)に贈与するという方法も考えられます。
3 相続時精算課税制度
相続時精算課税とは、合計2500万円分までは、贈与時に贈与税がかからず、相続の時に贈与時の評価額で相続税の計算の基礎に加算するという制度です。
2500万円分を現金で贈与する場合は、仮に、相続開始時において2500万円を相続税の計算の基礎に加算しますので、相続税対策としてはあまり意味がありません。
他方、値上がりが見込まれる土地や株式について、2500万円分相続時精算課税を利用して贈与しておけば、相続開始時にその土地や株式が値上がりしていたとしても、相続開始時において、相続税の計算の基礎として2500万円加算するだけですみますので、値上がり分だけ相続税を少なくできたことになります。
4 その他の贈与税の優遇制度
その他にも、国は生前贈与を勧めており、配偶者に対する贈与、住宅資金の贈与、教育資金の贈与、結婚子育て資金の贈与の場合に、一定の要件のもと、贈与税の優遇をしています。
5 生前贈与による相続税対策は税理士にご相談ください
生前贈与は、様々な制度をどのように利用するか判断に迷うことも多いですので、税理士にご相談いただきながら進めることをおすすめします。
また、関連する特例や制度は、都度改正が行われているため、最新の情報を把握することも重要です。
当法人では、生前贈与による相続税対策についてのご相談も承っております。
日頃から相続の案件を取り扱い、相続税を得意とする税理士がご相談に対応しますので、まず一度ご相談ください。