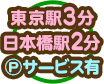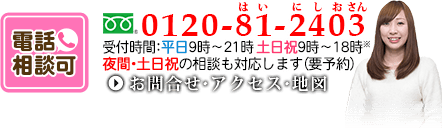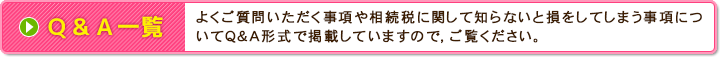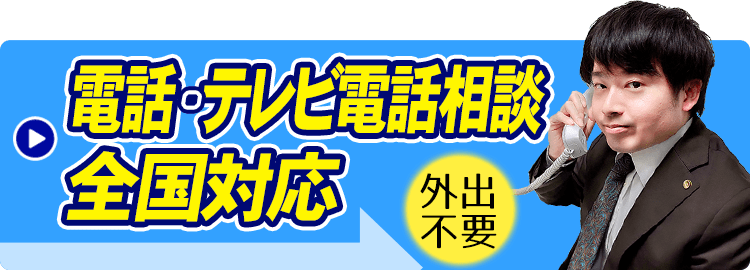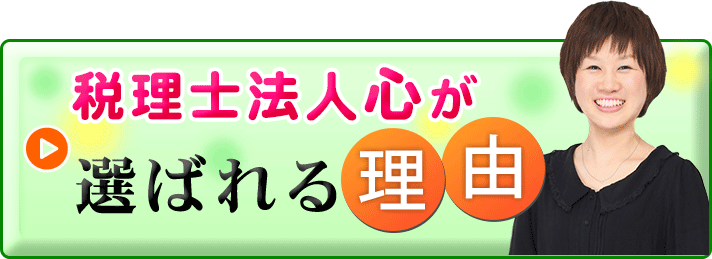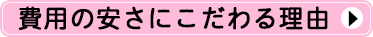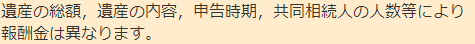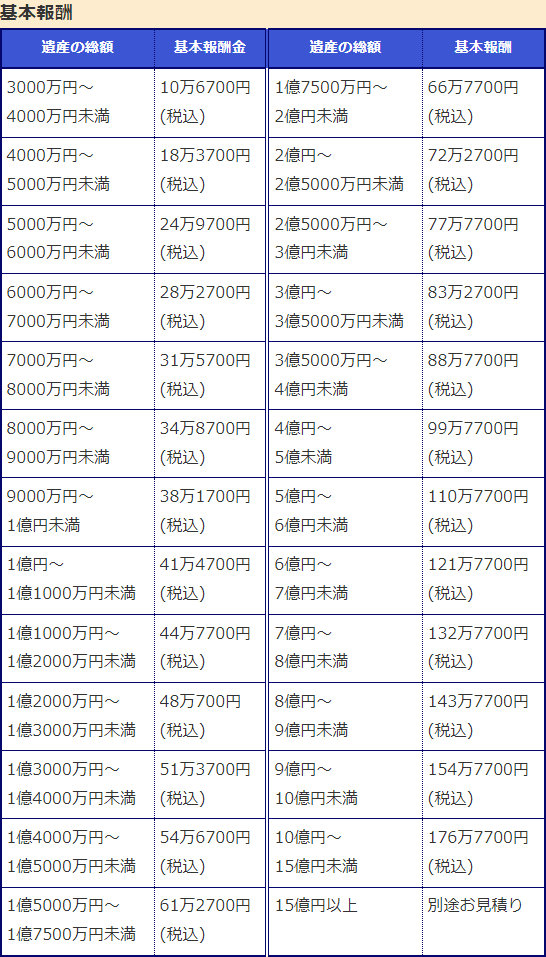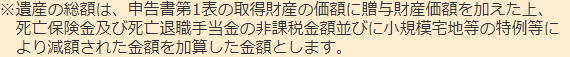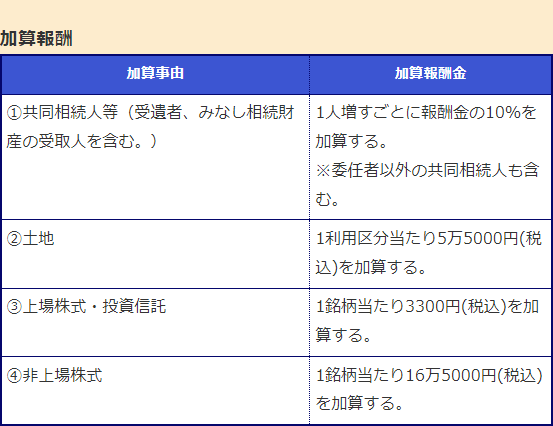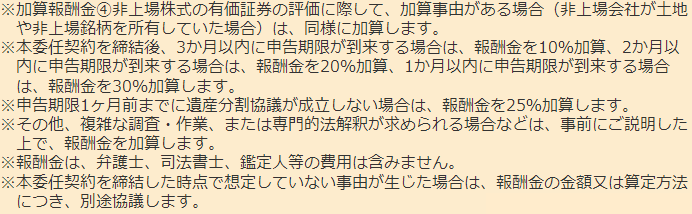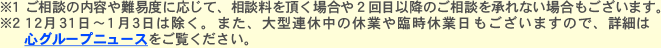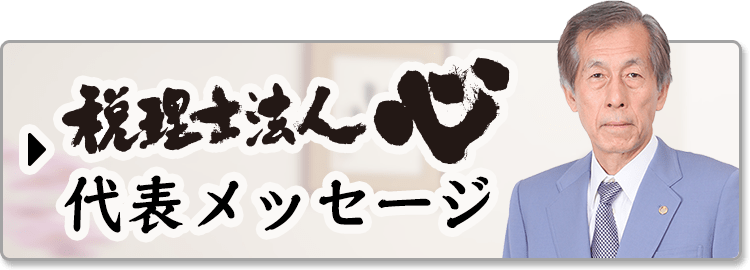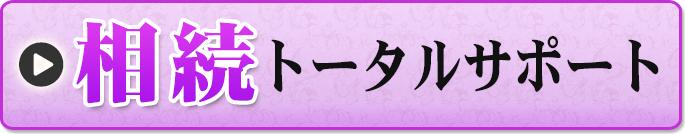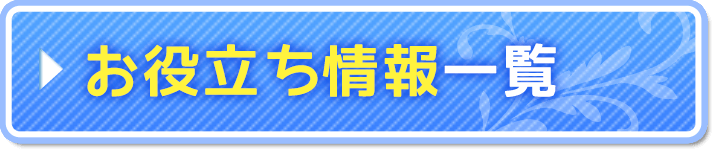お役立ち情報
生前贈与を活用した相続税対策
1 生前贈与が相続税対策になる理由
相続税は、被相続人が所有していた土地・建物、預貯金等の財産から、借入金、未払金等の債務を引いた後の金額に課税されます。
このため、被相続人が所有していた財産を減らすことができれば、相続税を軽減することができます。
被相続人が所有していた財産を減らす方法としては、被相続人が存命のうちから他の人に対して、まとまった財産を贈与することが考えられます。
贈与された財産については、被相続人の財産ではないこととなりますので、相続税の課税対象から外れることになります。
このように、生前贈与を行うことにより、相続時に課税される相続税を軽減できることが分かります。
2 生前贈与の工夫
もっとも、贈与された財産については、相続税とは別に、贈与税が課税されます。
贈与税は、各自が各年(1月1日から12月31日までの間)に贈与を受けた財産の総額が110万円を超える場合に課税されます。
贈与税については、相続税よりも税率が高くなっていますので、まとまった財産の贈与がなされることにより、かえって相続税よりも多額の税金が課される可能性があります。
したがって、生前贈与による相続税対策を行う場合には、贈与税に気を配りつつ、工夫して対策を行う必要があります。
どのように工夫するかというと、例えば、以下のようなものが考えられます。
ア 複数の人に分散して贈与を行うこと
贈与税は、贈与を受けた人が、その受け取った財産に対して課税されます。
贈与した側に課税されるのではありません。
したがって、複数の人が分散して贈与を受ければ、贈与税の課税を避けたり、軽減したりすることができます。
イ 毎年贈与を行うこと
贈与税は、各年に贈与を受けた財産に課税されます。
したがって、毎年、少しずつの贈与を行えば、贈与税の課税を避けたり、軽減したりすることができます。
3 生前贈与による相続税対策で気をつけるべき点
ただし、これらの相続税対策を行う場合には、様々な点に気をつける必要があります。
例えば、以下の点に気をつける必要があります。
⑴ 一連の贈与が一体のものと捉えられる可能性があること
毎年、少しずつ贈与を行った場合であっても、それが一連の贈与と捉えられてしまうと、多額の贈与税が課税される可能性があります。
例えば、10年間にわたり毎年100万円ずつ贈与者が贈与をしたとしても、贈与した最初の年に「毎年100万円を10年にわたって受け取る権利の贈与」があったとみなされると、当該権利の評価額に対して贈与税が課税されることになります。
このように一連の贈与とみなされないようにするためには、毎年の贈与の都度契約書を作成して、毎年贈与があったという証拠を残しておくという方法もあります。
また、贈与の日付や贈与額についても毎年異なるようにしておいたほうが無難といえます。
⑵ 贈与を受けたものと扱われない可能性があること
振込により贈与を行う場合は、入金後の口座が実際に贈与を受けた人が使っている口座であると認められる必要があります。
入金後の口座が、贈与を受けた人が使っている口座であると認められなかった場合には、その口座の中身は実質的に被相続人に帰属すべきものと判断され、相続税の課税対象とされる可能性があります。
そのため、現金や預金を贈与した場合、その現金や預金の管理は、贈与を受けた人が行うのがよいです。
また、贈与をしたという客観的な証拠を残しておくという観点からは、現金を手渡しするよりも、振込によって贈与を行うべきでしょう。
4 生前贈与による相続税対策に関するご相談
以上のように、生前贈与は相続税対策としては有効であるものの、様々な点に気をつけて行わなければ、かえって過大な税金が課税される事態を招く可能性もあります。
当法人では、生前贈与による相続税対策についてのご相談もお受けしています。
相続税を得意とする税理士がご相談を承りますので、まずはお気軽にご相談ください。
相続税申告の際の必要書類と集め方 相続税を軽減できる小規模宅地等の特例