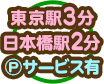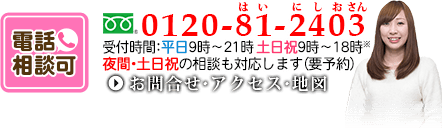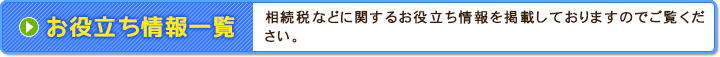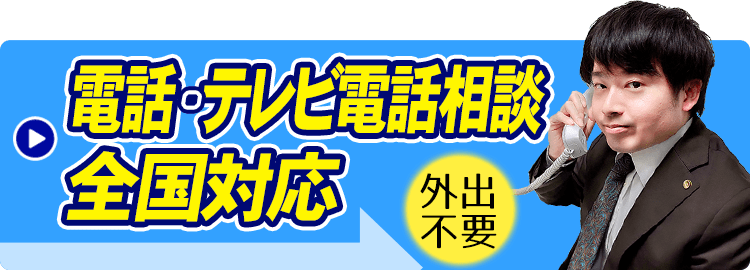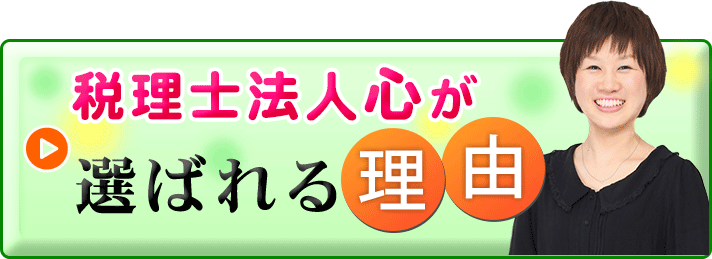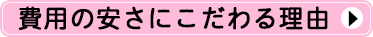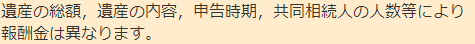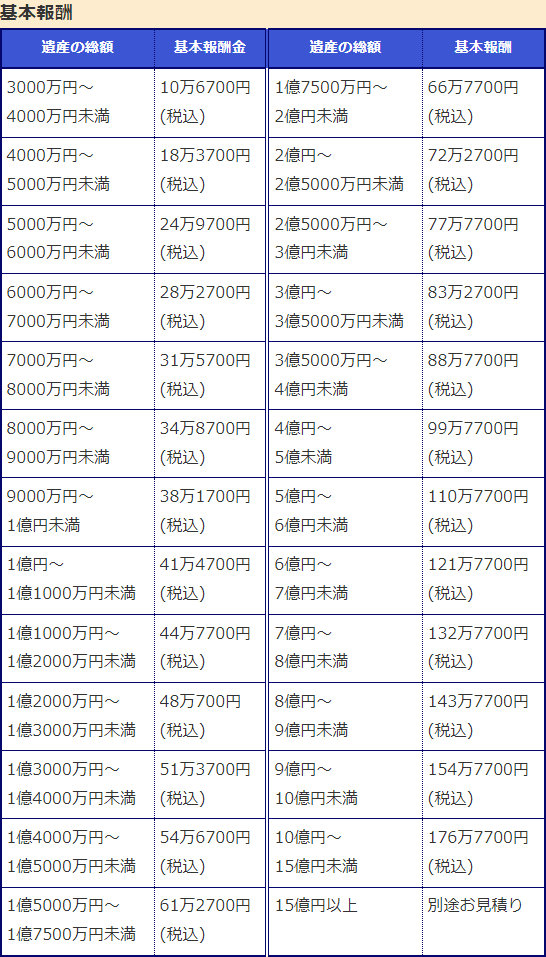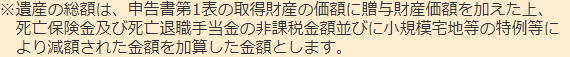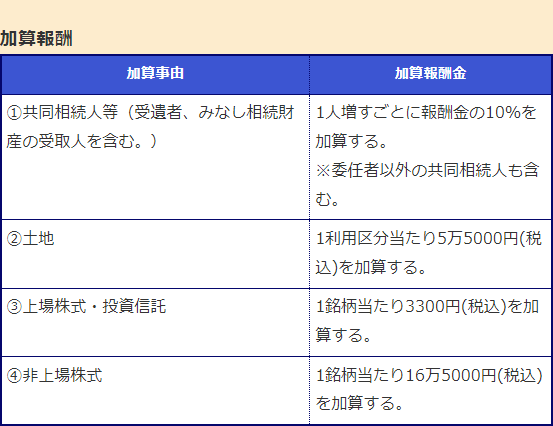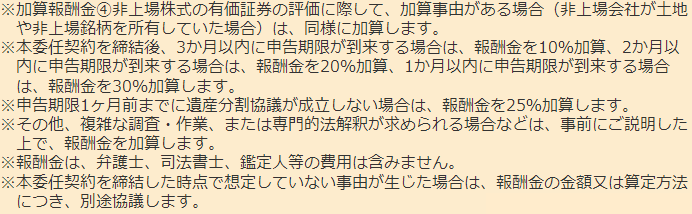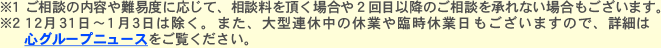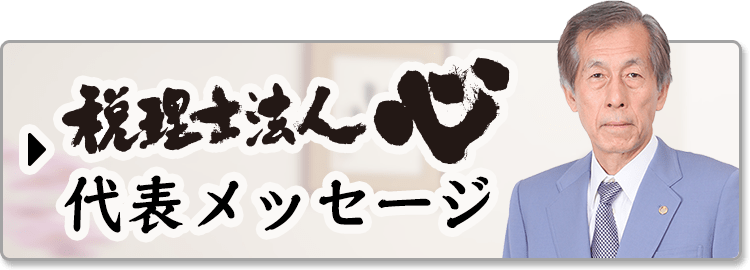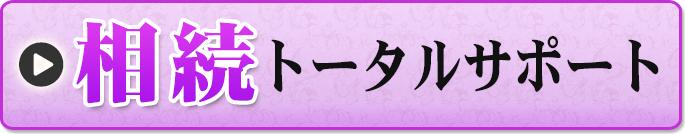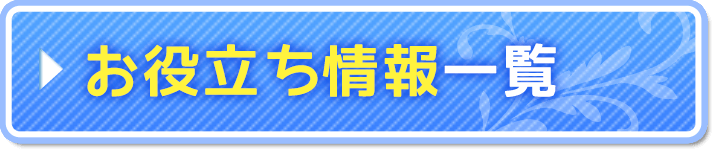相続税の2割加算に関するQ&A
相続税の2割加算とは何ですか?
相続税の2割加算とは、一部の相続人以外の人が相続、遺贈および相続時精算課税によって財産を取得した場合に、本来の相続税に加え、その人の相続税額の2割に相当する金額が加算される制度のことです。
加算の対象となるのは、財産を取得した人が、代襲相続人となった孫を含む被相続人の一親等の血族および被相続人の配偶者以外の人である場合です。
例えば、代襲相続人ではない孫に遺贈した場合や兄弟姉妹が相続人である場合などが、典型的な例として挙げられます。
本来であれば被相続人から子へ相続が起こり、その際に1回相続税を支払い、子から孫への相続の際にもう1回相続税を支払うことになりますが、被相続人から孫が財産を取得した場合には、同じ分のみ財産を取得したとしても相続税の支払いを1回免れることとなります。
また、法定相続人以外の人が財産を取得するのは偶然性が高いものであることなどから、国民の相続税負担の公平を保つという点が相続税の2割加算の趣旨であるとされています。
参考リンク:国税庁・相続税額の2割加算
相続税が2割加算される場合、どのように計算するのですか?
相続税の計算は、次の手順で行われます。
⑴ 被相続人の財産調査と金銭的評価を行う。
⑵ ⑴の金銭評価額をもとに、基礎控除等を行い、相続税の総額を計算する。
⑶ ⑵の総額を、各相続人の相続分に按分し、相続税率を掛け合わせる等により納付税額を計算する。
相続税の2割加算は、⑶の部分で行われます。
具体的には、財産を取得したそれぞれの人の算出相続税額にその20%相当額を加算します。
2割加算の対象になるのは誰ですか?
- ⑴ 対象になる人と対象にならない人
-
原則として、被相続人の配偶者および代襲相続人となった孫を含む一親等の血族以外の人は、2割加算の対象となります。
裏を返すと、夫または妻、子ども、父母のほか、代襲相続人となる孫は、2割加算に該当しません。
代襲相続人とは、相続人となる人がすでに亡くなっていた場合の、その相続人となる人のことをいいます。
代襲相続人となる孫とは、被相続人から見た子がすでに死亡していた場合の孫のことであり、一親等血族ではありませんが、例外として2割加算されないこととなっています。
養子も法律上は子の身分と同等となるため、原則として2割加算の対象とはなりません。
しかし、孫を養子にした場合(いわゆる「孫養子」)に限り、例外的に2割加算の対象となります。
これは、孫を養子にすると、その孫は、孫であるまま子から相続する1回分の相続を回避して、被相続人の遺産を受け取ることができるためです。
ただし、この孫養子にも例外があり、孫養子であっても、すでに被相続人の子が死亡している場合は、孫養子かつ代襲相続人にあたりますので、2割加算はされないとなります。
上記以外の人、具体的には兄弟姉妹、甥、姪、祖父母、代襲相続人ではない孫、内縁の夫や妻、友人や知人などの法定相続人以外の人は、2割加算の対象となります。
- ⑵ 相続時精算課税制度との関係
-
また、相続において、相続時精算課税制度が利用されることもあるかと思います。
相続時精算課税制度の手続きとメリットについては、こちらをご覧ください。
この場合、相続の開始時には被相続人の一親等の血族ではなかったとしても、相続時精算課税を利用した際の贈与によって財産を取得した時に、被相続人の一親等の血族となったのであれば、その財産に対応する一定の相続税額については加算の対象になりません。
相続税の2割加算の対象となる場合、税理士に相談したほうがよいですか?
以上のように、代襲相続が発生している場合や養子がいる場合など、誰が2割加算の対象となるのかは複雑になってきます。
さらに2割加算の対象となる人がいる場合、どの立場の相続人がどのような割合の法定相続分を持っているかなどの民法の知識も必要ですし、例外処理も多いことから、複雑な相続税の計算が必要となります。
万が一、計算時に2割加算が必要なことに気づかず、過少に申告してしまうと、後で加算税などが課されてしまうという危険性があります。
当法人には、相続税を得意とする税理士がおり、誰がどのように相続をすると、税額はどのように変わるのかなど、相続税の計算に関するご相談も承ります。
相続税にお悩みの際は、まずご相談ください。
自分で相続税申告を行うと税務調査の対象になるのですか? 相続代表者や代表相続人を決めないと相続手続ができないのですか?